「着衣のまま水に入るなんて…うちの子にできるの?」
そんな戸惑いの声が、保護者の心の奥から聞こえてくるのも無理はありません。
それでも、あえて挑戦する理由があるのです。
小学校6年間の学びを締めくくる、6年生の“着衣水泳”。
それは泳力を試すものではなく、“いのちを守る知恵”を身につける防災教育の一環。
濡れた制服をまといながら水に向かう子どもたちの背中は、自信と責任を背負った姿そのものでした。
着衣【水泳】における6年生!着衣水泳 ~命を守る力を育む最終レッスン~
もうすぐ小学校を卒業する6年生にとって、最後のプール授業は「着衣水泳」。
制服や体操服、靴下、場合によっては靴などを着けたまま水に入り、「泳ぎにくさ」「浮きにくさ」を実感することで、いざという時にどうやって命を守るかを学びます。
なぜ「着衣」で泳ぐのか?
- 衣類に水が浸透すると重くなり、いつもの泳ぎはできない…ほとんどの子どもが「思った以上に動けない」「体勢が崩れる」と驚くそうです。
- 体力を温存しながら「浮く力」を活用することが大切だと実感できる、貴重な体験になります。
実際の流れ
- 普段の水着で泳ぐ → 着衣の状態に切り替えて、動きの違いを体感。
- 背浮きの訓練 → 顔と脚を水面に出す姿勢(背浮き)をゆっくり練習。
- 浮くものの活用 → ペットボトルやバケツなど身近なものを浮具として使い、体を浮かせる方法を学ぶ。
- 脱衣体験 → 水中で衣服を脱ぐ訓練も併せて行い、水の抵抗から解放される感覚を味わう。
体験者の声
- 「ズボンが重くてなかなか進まない」
- 「服だけでも浮くけど、泳ぎにくい!」
- 「ペットボトルを抱えると落ち着いて浮けた」
まとめ
この体験を通じて、子どもたちは「水に落ちた時には泳ぐより“浮いて待つ”ことが命を守る鍵」という大切な教訓を学びます。
川や海で万一の事故に遭った際に、パニックにならず、自分の身の守り方を即座に判断できる力を、6年間の集大成として身につけているのです。
★茨城新聞、県内の小学校で「浮いて命を守って」のタイトルで2025年7月9日に掲載されました。

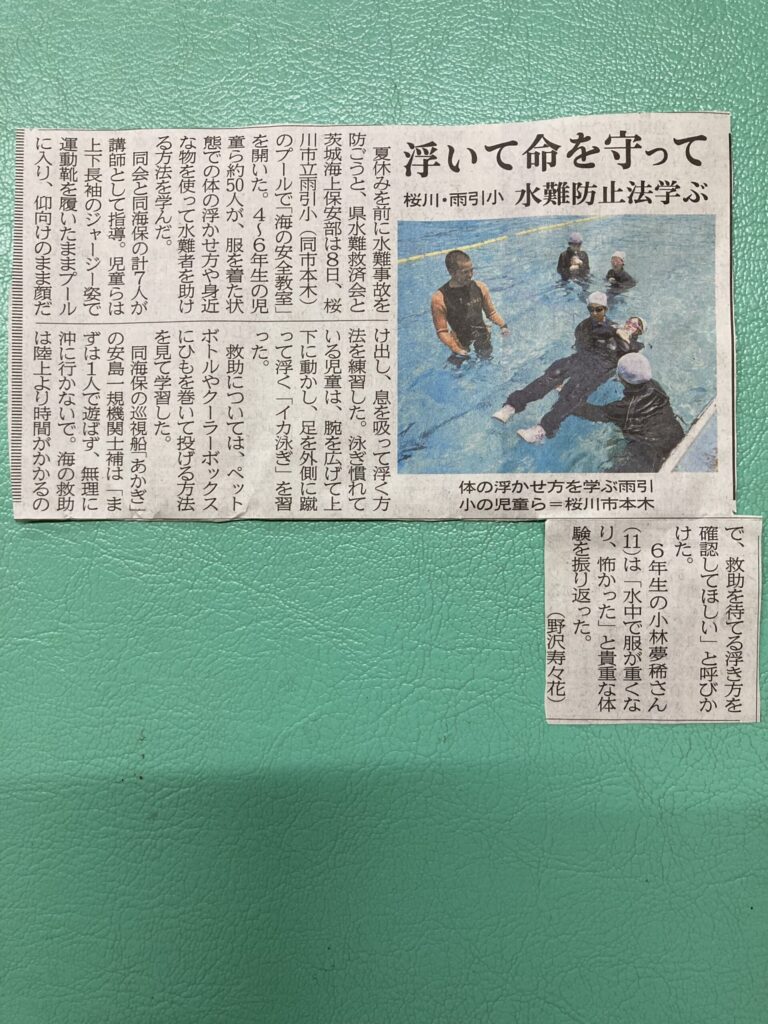
着衣【水泳】における6年生!:なぜ今「着衣水泳」が必要なのか?
日本は水に囲まれた国。毎年、川や海での事故が後を絶ちません。
文部科学省によると、小学生の水難事故の多くは「遊泳中」ではなく、「服を着たままの転落」や「流されて溺れる」ケースです。
つまり、「泳ぎが得意=安全」とは限らないのです。
着衣水泳の目的は、水中での“パニックを防ぐ”こと。そして、“助けを待つ術”を身につけることにあります。
6年生にしかできない“命の学び”とは
着衣水泳は、全学年で行われる学校もありますが、とくに6年生にとっては意味が違います。
なぜなら、それは「集大成の授業」だからです。
・浮くための姿勢
・体力を消耗しない呼吸法
・助けを求めるための声の出し方
・ランドセルを使った浮力確保の実験
・“助けようとせず、大人に助けを呼ぶ”判断力
これらのスキルを、実践を通じて学ぶのです。
そしてそこには、「自分の命を守るだけでなく、周囲の命を脅かさない」という責任感も育まれます。
現場レポート:6年生たちのリアルな姿
「よーい、はじめ!」
笛の音とともに、服を着たままの子どもたちがプールに入っていく。
シャツやズボン、スカートが水を吸って重たくなり、思うように動けない。
最初は戸惑いながらも、子どもたちの表情は徐々に変わっていきました。
「思ったより体が沈まない!」
「シャツに空気が入ると浮くんだね!」
「ジタバタすると逆に沈むんだって!」
見守る先生たちも声をかけます。
「慌てないで!仰向けになって、空を見てごらん!」
「浮くだけでいい。泳がなくていいんだよ!」
一人の男の子は途中、うまく浮けずに焦り、泣きそうな顔になりました。
でも隣の子が、そっと声をかけます。
「だいじょうぶ、一緒にやろう。」
その一言で、彼は再び体勢を整え、ゆっくりと浮かび始めたのです。
子どもたちの心に残った言葉と経験
授業のあと、子どもたちに感想を聞きました。
「もし川に落ちたら、前は泳ごうとしてパニックになってたと思う。
でも、今は浮いて待てる気がする。」
「助けるつもりが、溺れちゃうこともあるって初めて知った。
だから『呼びに行く』って大事なんだなって思った。」
「最初は怖かったけど、服が水を吸って重たくなるって実感してよかった。
楽しかったけど、命のことって感じた。」
この“体験”こそが、命を守る力になる。
教科書では伝わらない実感が、彼らの中に確かに残っていたのです。
①子供体験談:水に入った瞬間、心までズシンと重くなった
6年生の最後のプールの日、「今日は制服のまま入ります」と先生に言われたとき、正直ちょっとワクワクしていました。
いつもと違うことができるって、なんか特別な気がしたからです。
でも、いざ水に入ると、足が一気に重くなって、ズボンが水を含んで体にまとわりつく感覚が、思った以上に怖かったです。
泳ごうとしても全然前に進めないし、息も上手く吸えなくて焦ってしまいました。
「仰向けになって浮いてごらん」と言われても、最初はなかなかうまくできませんでした。
でも、シャツに入った空気で少し体が浮いたとき、「あ、浮けるんだ」って思えたのを覚えています。
ペットボトルを抱えたとき、急に安心した感じがして、「泳ぐんじゃなくて、浮くことが命を守るんだ」って、やっと意味が分かった気がしました。
今日の授業、ちょっと怖かったけど、自分の中で“命を守る力”が育った気がします。
②子供体験談:「大丈夫?」って声が、自分を支えてくれた
水に入った瞬間、制服が冷たくて体にピタッとくっついて、「うわ、気持ち悪い!」って思ったのが第一印象でした。
少しずつ進もうとしたけど、服が水を吸って重くなり、動くたびに体が沈んでいく感じがして、すごく怖かったです。
途中、本当に浮けなくて、焦って水をバシャバシャしてしまいました。
そのとき、隣にいた友達が「大丈夫?」って声をかけてくれて、なんとか心を落ち着けて背中を水に預けられたんです。
その一言がなかったら、きっともっとパニックになってたと思います。
ペットボトルを抱えると、なんだかフワッと体が軽くなって、少しずつ呼吸もできるようになりました。
あの時感じた安心感は、きっと一生忘れません。
今日の授業で、「助けてもらうこと」や「声をかけあうこと」の大切さを知った気がします。

私自身、子供時代に水に溺れた経験が2回あります。
最初は、小学校へ入る前、氷の張った川を渡ろうとして氷が割れて溺れましたが、近所のおじさんに助けて貰って命拾いしました。
指導者・保護者の視点で考える「命の教育」
指導する側も、ただ技術を教えるのではありません。
大切なのは「判断力」と「冷静さ」を育てること。
実際に、学校現場では「助けようとして一緒に溺れることがある」ケースも伝えられています。
だからこそ、教えるべきは「勇気ある“助けない”選択」。
保護者の中には「わざわざ危険なことをさせる必要があるのか」と不安視する声もありますが――
むしろ今、あえて“安全な環境で危険を体験”させることが、生きる力を育む教育なのです。
①親体験談:息子の姿に、“生きる力”が見えた瞬間
「服を着たままプールに入るなんて、大丈夫なの?」と正直思っていました。
息子は泳ぎが得意な方ではなく、体育の水泳授業もいつも「疲れた」と言って帰ってくる子です。
でも、授業の様子を見学していると、初めて見る真剣な表情で水に入っていく姿に、思わず胸が熱くなりました。
最初はバランスを崩して水を飲んでいたようで心配でしたが、先生や仲間の声かけに支えられ、徐々に背浮きを成功させる様子は、本当に頼もしかったです。
後で「ペットボトルって、すごく浮くんだよ」と興奮気味に話す息子の目は、自信に満ちていました。その姿を見て、「ただの授業じゃない。これは命の授業だ」と感じました。
②親体験談:泳ぎの上手さよりも、冷静さが命を守る
着衣水泳の授業の日、娘は「今日、ちょっと緊張するかも」と言いながら家を出ました。
服を着たまま水に入るなんて、親としてはやっぱり心配でした。滑ったり、足を取られたりしないだろうか、と。
でも、帰ってきた娘が「服が重くて全然泳げなかったけど、浮けた!」と笑顔で話してくれたとき、心の中で何かが変わりました。
「焦ると沈む。ゆっくり浮く方が安全なんだって」と語るその言葉に、体験からくる確かな“理解”が感じられました。
着衣水泳の本当の意義は、子ども自身が命を守る選択肢を知り、備えることなんですね。
泳ぐ技術より、冷静に行動できるかどうか・・・親としても勉強になった一日でした。

現在は祖父の立場です。
自宅周りは水辺が多い地域なので、孫の水難事故が心配になります。
着衣泳にはとても関心があります。
着衣【水泳】における6年生!:まとめ
6年生という年齢は、「子ども」と「大人」の間にある特別な時期。
社会や命のことに対して、現実味を持って考えられる最後の小学校生活。
そのタイミングで「着衣水泳」を通じて、自分の命、仲間の命、家族の命――
そのすべてを守る“最初の力”を体に刻む。
泳ぎの得意・不得意ではありません。
最後まで浮き、声を出し、あきらめない。
それが命をつなぐ手段であり、それがこの授業の本質なのです。
「命を守る力は、知識や筋力よりも、冷静な心が育てる。」
この言葉を胸に、子どもたちは一歩ずつ、次のステージへ歩み出していきます。



コメント